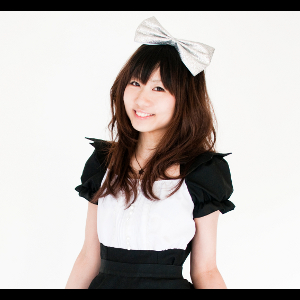さやわかの「プロデューサー列伝」 第8回:Revo(Sound Horizon)
紅白こそRevoにふさわしい舞台 物語音楽の旗手Sound Horizonが目指すものとは?
Revoがコミケや「とらのあな」のような同人ショップでCDを頒布するようになったのは2001年以降のことだ。90年代末からゼロ年代初頭というこの時代は、従来から知られていたマンガ同人誌だけでなく、かねてよりのITブームで個人でも安価で作れるようになっていたゲームや音楽CDなどの発表場所として、同人シーンが飛躍的に拡大していた。だからこの時期にRevoが同人市場へ足を踏み入れたことは、全く不思議なことではない。
彼がスタートさせた「Sound Horizon」という一人ユニットは、最初期にはファンタジックな世界観、打ち込みを用いた音楽性、ユニット名を囁くサウンドロゴなど、様々な点でゲーム音楽のようだった。架空のロールプレイングゲームのサウンドトラックというコンセプトで作った作品なのだと言われたら、なるほどそうかと思ったかもしれない。だが音楽シーンに沿わせた言い方をすれば、これはたとえばドイツのハロウィンやイタリアのラプソディーなどが展開していたファンタジックな世界観を下敷きにした、時にシンフォニックなメタルを、日本のRPGの世界観に置き換えるというアイデアを感じさせる。
ただ、その後Sound Horizonはそこから独自の路線へと変わっていく。まずRevoは必ずしもメタルという音楽性に固執しなかった。彼はむしろ曲中で語られるべき物語を余さず表現するために曲調やコード、リズムを選ぶようになり、歌詞の展開に合わせて一曲の中で劇的に曲のテンポやジャンルそのものを変えてしまうことも厭わなかった。しかしならばそれがミュージカルとか劇伴とか、ロッカペラの類なのかと言われればそうではない。彼はあくまでポップミュージックの範疇で、言ってみればどんなリスナーでも通して聴くことのできるポップスらしさを守りながら、しかし全体としては「物語を伝える」という機能を持った曲を作り始めたのだ。当時、そんな音楽はどこにもなかった。
つまりSound Horizonは唯一無二の存在で、どれだけ近い音楽性を持ったグループがあろうとも音/物語作りの根幹の部分で他と異なっている。それなのにRevoはあくまでもポップス、つまり大衆性を心がけている。その不思議なバランスじたい、独特のものがある。
違う見方をすれば、Revoのやり方は、いわば音楽と物語を不可分にしていると言うことができる。楽曲で物語を表現することには、もちろん普通の音楽にはあり得ない困難がつきまとう。だが曲と物語を渾然一体にすることができれば、音楽の特性を活かして人々の最も深い部分へ物語を叩き込むことができるのだ。しかも歌詞カードには文字表記に至るまで含意があり、また曲ごとに描かれる印象的なシーン、ジャケットやブックレットで提供されるビジュアル、そして時としてアルバム全体に隠された謎の存在などと相まって、Revoの音楽は、いやSound Horizonの"物語音楽"は熱心なリスナーの熱狂を誘うようになった。