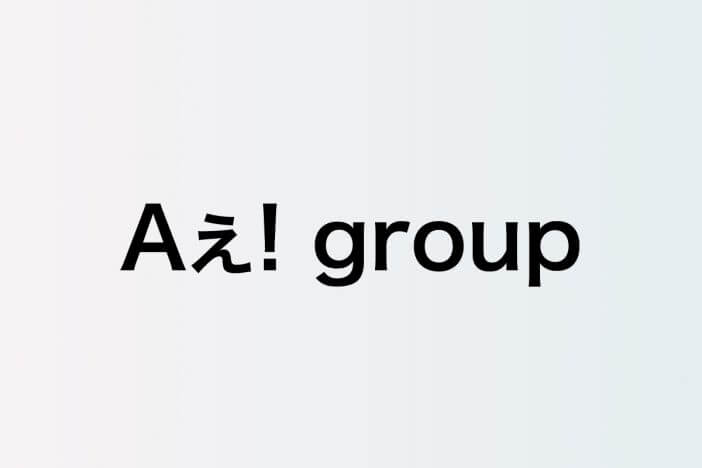Dragon Ashがたどり着いた“迷いなき場所” 激動の創作ヒストリーから読み解く
Dragon Ashの新アルバム『THE FACES』が1月15日にリリースされ、ロックシーンにおいて高い評価を得ている。同グループにとって約3年ぶりのオリジナルアルバムとなる本作は、2012年にベースのIKUZONE氏が急逝するというバンドの危機を乗り越え、現メンバー6人が「The Show Must Go On(それでもショーは続く)」というスローガンを掲げながら作り上げた、入魂の一枚である。
Dragon Ashにとってシンボリックの意味合いを持つ「百合」を曲名に冠した新曲「lily」を始め、IKUZONE氏への追悼の意志を感じさせる「The Live」や、ラストを温かく締め括る「Curtain Call」など、凛々しくも重厚な全14曲を収録した本作は、バンド結成18年にして「最高傑作」との呼び声もあるほどだ。
音楽ライターの麦倉正樹氏は、Dragon Ashが『THE FACES』に至った道筋について、次のように語る。
「ミクスチャー・ロックの代表的なバンドとして認知されているDragon Ashですが、2000年あたりから『ミクスチャー・ロック』というジャンルのイメージが一人歩きし、ポジティブな印象とネガティブな印象の両方を引き受けた面があったと思います。2005年にリリースした6枚目のフルアルバムである『Río de Emoción』でラテン調の曲風が強くなったのは、彼ら自身の手でミクスチャーを再定義する意味合いもあったのではないでしょうか」
その後にリリースされた『INDEPENDIENTE』もまた、ラテンの流れを汲む作品だった。そして2009年には、Dragon Ashの名前を世に知らしめたアルバム『Viva La Revolution』と対になる作品として、従来のスタイルとラテン系の陽気なグルーブが無理なく融合した『FREEDOM』を、翌年にはラウドロック的な色の濃い『MIXTURE』をリリースした。