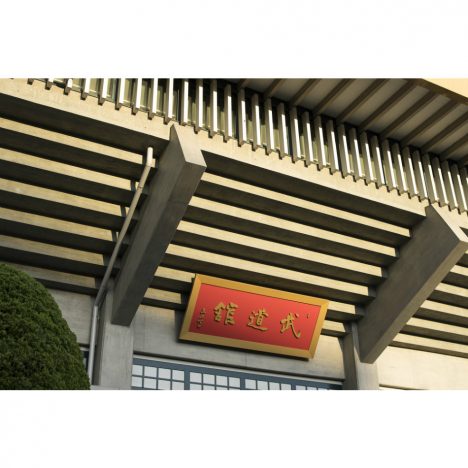『NEW TRIBE』リリースインタビュー
「ギターとビートでまだ面白いことができる」a flood of circleが敏腕エンジニアと探究した“強さ”

a flood of circleがニューアルバム『NEW TRIBE』をリリースした。
結成から10年以上を経て、日本を代表するロックンロール・バンドの一つとして確かな存在感を築き上げてきた彼ら。その一方、過去に当サイトで掲載されたインタビュー等でも明らかになっている通り、フロントマンの佐々木亮介(Vo/G)はヒップホップやエレクトロも含めた海外の同時代的な音楽シーンに鋭くアンテナを張り、そこからの刺激を自らの音楽に還元しようとしている貪欲なミュージシャンでもある(参考:a flood of circle佐々木亮介が表明する、“ロックンロール”への危機感「一番ポップな部分から、バンドが置き去りにされてる」)。
新作は、ロンドンの名門スタジオ「メトロポリス」でリアーナやデヴィッド・ゲッタなどのエンジニアリングをつとめてきた敏腕エンジニア、ザブ(ザビエル・ステーブンソン)と共に作られた一枚。どんな刺激があったのか? 佐々木亮介、渡邊一丘(Dr)の二人に話を聞いた。(柴那典)
「バンドのレコーディングの線引きが微妙な時代だと思っていて」(佐々木)
――新作『NEW TRIBE』を聴いて、すごく攻めたものになっている印象がまずあって。バンドの10周年を経て、新しいアートフォームを作ってきたなと思ったんですけれど。
佐々木:まさにそうです。
――アルバムの制作は最初に「BLUE」「El Dorado」「Flyar’s Waltz」の3曲をロンドンでレコーディングをしたことが始まりだったんですよね?
佐々木:ベスト盤を出すことが決まったくらいから、そこをゴールにせずに新しいことをしたいと決めていて。で、ロンドンに行こうという話になったんです。やるならどういう音を作ろうかと、いろんなスタジオを考えて。パブロックやガレージロックに強い、狭いけど生々しい音を録るスタジオとか、The White Stripesを録っているスタジオとか、アビーロード・スタジオとか、いろんな候補があったんですけど。
ーーメトロポリス・スタジオを選んだ理由は?
佐々木:メトロポリスは歴史もちゃんとあるけど、新しいものを作ってるんですよね。俺たちがロックンロールを更新しようとしていることが伝わりそうだなと思ったし、バンドが先に進めそうな感じがしたんです。
――アルバムはアデルやリアーナも手掛けているザビエル・ステーブンソンがエンジニアリングを手掛けています。彼との出会いは?
佐々木:スタジオに初めて行ったときに紹介されたんですよ。誰になるかわからなかったんですけど、ザブは以前にもユーミンさんや葉加瀬太郎さんと一緒にやったことがあって。だから日本人に抵抗がなかったのかもしれない。
――これは僕の推測ですけど、「ロンドンの人たちにナメられたくない」という気持ちは最初にあったんじゃないか、と。
佐々木:そりゃそうですよ。そのへんは、育ちの悪さがあるんで(笑)。でも、幸いザブが心を開いてくれて。「いい音楽を作るためにこのプロジェクトはあるんでしょ」っていう考えのもとに生きてる人だったので、「俺のプライドなんてしょうもない」と気付かされたし、言語レベルでもお互い歩み寄れたし。
――どういう気付きがあったんでしょう?
渡邊:実際、細かいところで本当に沢山あったんですよ。最初にあったのが「El Dorado」のテンポが倍になるところなんですけど。今まで、リズムセクションはせーので録ってたんですよ。でも今回はドラムから一つずつ録っていく形になって。
佐々木:最初は人工的な音になったらどうしようと思ってたんですけど。そこで一回ナベちゃんとザブがぶつかってね。
渡邊:ズレないように叩こうと思ったんですよ。時間もないし、作業も少なく済むように、正しいドラムを叩こうとしていて。そうしたらザブに「お前は力いっぱい叩くのがいいんだよ!」と怒られて。で、ザブの意見を飲んでやったら、めちゃめちゃいい出来になって。俺としてはそこでちゃんと初めてディスカッションできて、「ちゃんと曲について考えてくれてるな」と思った。
佐々木:セッションを記録するんじゃなくて、プロダクションとして組み立てていくのがレコーディングだ、という発想なんですよ。でも、今って、バンドのレコーディングの線引きが微妙な時代だと思っていて。
ーー微妙というと?
佐々木:生っぽくないとつまんないし、かと言ってプロダクションとして組み立てる要素がないと、ただのセッションになって広がりがなくなる。線引きをどこにするのか難しいんですよね。でもザブは、タイム感も、音の置き方も、絶妙だったんです。きっちりしてるけど生っぽいっていう。「リアーナとかとやってたことはこれか!」って思って。デヴィッド・ゲッタみたいにプロデューサーが作った音をミックスすることも、生のバンドのレコーディングもやってるし。世界規模でプロなんですよね。
渡邊:スティングもやってるしね。
――で、最初にその3曲を作って日本に帰ってきた。
佐々木:そうです。その後にアルバムのレコーディングの話になって。ナベちゃんが「絶対にザブとやりたい」と言って。でもロンドンに行くスケジュールもないし。いろんなアイデアがある中で、じゃあザブが日本に来るならアリだということになって。
渡邊:10年目のわがままです(笑)。
――渡邉さんがザブと一緒にやることにこだわった理由は?
渡邊:ザブから得た新しいエッセンスが重要だと思ったんですよね。過去に縛られたくないと思ったし、新しい感じをアルバムにして届けたいと思ったから。「El Dorado」がとにかく良かったんですよ。ミックスされた音源を聴いて「これ、俺なら買うわ」という第一印象が真っ先に出たくらいだったので(笑)。
――サウンド的なところでは何が大きかったですか?
渡邊:個人的には、今まで好きで聴いていた洋楽のドラムの音を出してもらえたというのがあったかな。輪郭や低音、立体感というか。ただドラムがくっきり聴こえるだけなら、他のギターやベースやドラムが凹んで聴こえると思うんですけど、しっかりと全ての音が支え合ってて、絶妙なバランスがあった。
――佐々木さんもその感覚は共有していた?
佐々木:そうですね。ザブとやるならこうしたいとか、ザブありきで考えることもできたし。ザブに「もう一回会おうね」って言ったのも、社交辞令じゃなくてマジでやりたかったし。まあ、正直それはすぐじゃなくてもいいと思っていたけど、ナベちゃんの気持ちがあるなら今だなって。
――で、東京に来てくれとオファーした。これは向こうにとっては異例なことだった?
佐々木:らしいですね。メトロポリスには一回断られたんです。でも単純にザブとめっちゃ仲良くなったんですよね。だからOKしてくれたと思うんですけど。
――仲良くなったというのはどういう感じで?
佐々木:いい意味で音楽的にハマってくれたというか、俺たちがやろうとしてたことをわかってくれた感じなんですよ。例えば「El Dorado」だったら、例えばLed Zeppelinみたいなブルース・ロックのルーツがあって、その後ヒップホップが出てきて、それが混ざってミクスチャーロックみたいになる時代があったじゃないですか。そのミクスチャーロックがなくなってきたのが今という時代で。その後に、自分たちが思ってるブルース・ロックとヒップホップの新しい融合ができないかなと思ってたんです。そういう中でカニエ・ウエストの話をしたりもして。あと、彼はMastodonみたいなマッチョな音作りが好きなんですよ。イギリスの若手バンドをプロデュースしてるんですけど、それもヘヴィでラウドなものなんですよね。その感じが、俺たちの音のイメージとハマって。