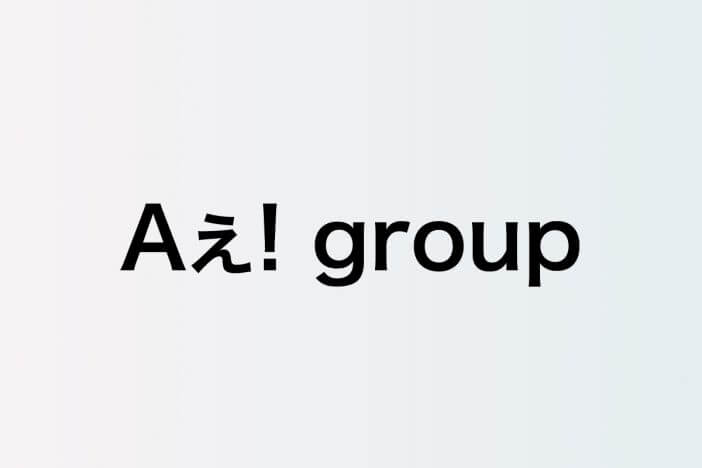Flowerが作り上げる、ステージでの“総合表現” 『たいようの哀悼歌』収録ライブ映像を見て

Flowerの最新シングル『たいようの哀悼歌』(初回生産限定盤A)付属のDVDには、表題曲のMVとともに、今年1月に催されたライブ『Flower Theater 2016 ~THIS IS Flower~ THE FINAL』の映像が収録されている。Flowerの表現は常に、ボーカルとパフォーマーが織りなす特有のバランスを軸にして展開される。その意味では、楽曲のみではなくライブパフォーマンスを知ることによってこそ、彼女たちの目指す射程が見えてくる。今回のリリースでワンマンライブの全容が収められたことを機に、Flowerが作り上げる表現を再確認してみたい。
収録されているライブは、Flowerの2ndツアーファイナルの模様である。ツアータイトルには、ライブに先立ってリリースされていたベストアルバム『THIS IS Flower THIS IS BEST』からのフレーズ「THIS IS Flower」が用いられているが、彼女たちのライブの歩みを考えるとき、より長期のスパンで意味をもつのは、タイトルの頭に冠された「Flower Theater」の方だろう。
2015年に催された初の単独ツアー『Flower LIVE TOUR 2015“花時計”』でもこの言葉は掲げられ、“劇場”の中で箱庭的な世界観を色濃く構築した。そして、2ndツアーに引き継がれたこのコンセプトを、彼女たちはさらに大きく育ててみせる。今回のライブ映像に映し出されているのは、前年のツアーよりもさらに“Theater”の意味を拡張して体現する6人の姿だった。
ボーカル、パフォーマーとプロジェクションとの繊細なコンビネーションで「花時計」の世界を彩ってみせた前年と比べて今回のライブが特徴的なのは、冒頭の映像で使用される映写機のイメージやフィルムを模したツアーロゴといった、映画館(=Theater)モチーフである。また、映画的イメージをより強くするのは、ライブパフォーマンスと交互に上映される映像群だ。グループの作詞を手がける小竹正人が紡ぐストーリーに導かれ、楽曲のキーとなるフレーズを随所に織り込んだそれらの映像は、生身のパフォーマンスの合間を有機的につないでゆく。いくぶんクラシカルなシネマのイメージを意匠として背負うことに関していえば、LDHの各グループの中でもFlowerが最も適任なのかもしれない。
もっとも、初の単独ツアー開催時から「Flower Theater」を掲げていた彼女たちにとって、「Theater」の意味はより広いものである。2015年のツアー同様にステージの外枠を白く縁取り、額縁舞台としての劇場空間(=Theater)を作り出すと、その中でボーカルとパフォーマーとが同等の存在感をもって立体的な表現を展開する。もとより、パフォーマンスの重点が歌唱のみに置かれない複合的な表現を、LDHという組織はいくつもの形で繰り返し表してきた。Flowerのワンマンライブでは歌唱と身体的パフォーマンスに加えて、ダンスに連動したプロジェクションや具体的なストーリーを補完する映像までも連関させ、さらに総合表現としての形を追求していく。この表現形式によって、彼女たちが持つ叙情性は最大限に引き出される。
もちろん、その総合的な表現の芯には、6人それぞれの等身大のパフォーマンスがある。パフォーマー一人一人とボーカルの鷲尾伶菜とが一対一で表現する楽曲群では、6人体制になって以降のFlowerの、個々としての強さをうかがい知ることができる。「紫陽花カレイドスコープ」では坂東希、「太陽と向日葵」では重留真波、「初恋」では中島美央、「さよなら、アリス」では佐藤晴美がそれぞれに鷲尾とのタッグでパフォーマンスし、藤井萩花は「CALL」でピアノ演奏、「白雪姫」でメインダンスをとる。いずれもボーカルとパフォーマーとが単純な主従や大小の関係に収まることのない、同等で不可分の関係を描いてみせる。一対一のタイトな編成から、映像と連続させた表現まで、複合的なパフォーマンスを体現する場。それこそが「Flower Theater」であり、彼女たちの秀逸なバランスをもっとも堪能できるステージである。