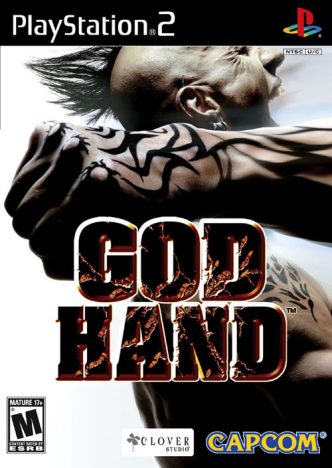ゲームをやり続けることに意味はあるのか? 『レディ・プレイヤー1』が問いかけるもの

政治機能が崩壊し、自然破壊でめちゃめちゃになった2045年の世界。厳しい現実にさらされる多くの庶民が求めたのは「仮想現実」“VR(バーチャル・リアリティ)”への現実逃避だった…。かつて万国博覧会で展示され、子ども向け雑誌などで描かれた、明るく希望にあふれた未来予想図とはだいぶ異なり、映画『レディ・プレイヤー1』で描かれる仮想現実世界“OASIS(オアシス)”は、困窮した人々が生きる「現実」の暗い影を背負っている。
そんな人々が、ウェアラブル・ギア(装着型接続機器)を駆使し、荒んだ家の中で日夜を問わずVRに逃避している姿を、本作は冒頭で悲哀とユーモアを込めて見せていく。彼らは一体、仮想現実で何をやってるのか。それは、きらびやかなポップカルチャーに囲まれたテーマパークのような“OASIS”を舞台に、自分の理想の姿を投影した「アバター」に乗り移り、ギャンブルやバトルゲームなどによって現実世界で換金できるコインやアイテムを奪い合ったり、プレイヤー同士で交流をしたり…。

そんな世界に「希望」はあるのだろうか。アーネスト・クラインの原作小説を、スティーヴン・スピルバーグ監督が映画化した本作『レディ・プレイヤー1』は、その問題に迫った作品になっていた。ここでは、描かれたテーマについて考えながら、示唆されるゲームやVRテクノロジーの未来にとって重要なことを考えていきたい。
難攻不落のゲームに挑むプレイヤーたち
本作は、宝を探す冒険物語である。OASIS創始者、ジェームズ・ハリデー(マーク・ライランス)は死に際して、自身の財産である、OASISの所有権と5000億ドルを、ゲームの隠し要素を示すスラング 「イースター・エッグ」と名付けられたアイテムにして、OASIS内のどこかへ隠したと、大々的にアナウンスする。それを獲得するためには、超難度のゲームをクリアし、3つの鍵を手に入れなければならない。
だが、第1の鍵を手に入れるための関門である、キングコングが割り込んで理不尽な攻撃を繰り出してくる謎のレースゲームがあまりにも難し過ぎたために、誰もクリアできないまま数年が過ぎてしまっている。多くのプレイヤーはイースター・エッグ探しに興味をなくし、いまやOASISの所有権をねらう大企業が編成するチームと、酔狂なゲームマニアくらいしか挑戦者がいなくなってしまったのだ。
難攻不落のゲームをマニアがこぞって解き明かそうとする事例は、実際に存在する。古くは、家庭用ゲーム機「アタリ2600」用ソフト『SwordQuest(ソード・クエスト)』シリーズ(1982〜)がある。これは、ゲームに隠されたキーワードを見つけ出して期間内にゲーム会社にそれを郵送すると、宝石がいくつも散りばめられた「聖杯」や「王冠」など、数万ドル相当の本物の宝が獲得できるというものだった。第1回大会で謎を解いたプレイヤーは8人。本社で決勝戦を行い、その中の一人が優勝し、現実世界で宝をゲットしたのだという。
現代では、商品は無くともゲーマーとしての名誉のために、難関ゲームに挑む者たちがいる。ゲームクリエイター小島秀夫が、映画監督のギレルモ・デル・トロとともに作るはずだった、『サイレントヒル』シリーズ新作のプロモーション用ホラーゲーム『P.T.』(2014)は、話題作りのためにあまりにも不親切で難解な謎を用意し難易度を上げたが、複数のゲーマーが数時間でクリアしてしまったことがさらなる話題となった。その後多くのプレイヤーがクリアすることができたが、これらを可能にしたのが、インターネットの交流によるプレイヤーたちの集合知である。
『バイオハザード7』体験版(2016)に至っては、クリアできるようにアップデートされるまでは、どうやってもゲームオーバーにしかたどり着けない仕様だったが、ゲームオーバーへと至る演出を回避できるバグをあるプレイヤーが見つけてしまったため、「これはもしかしたらクリアできるのかもしれない」と、世界中の暇なゲーマーたちが、作品の舞台となる家の中を延々と歩き回り、やれる限り全ての行動を試して時間を無駄にした。
なぜ1980年代にこだわるのか
話を『レディ・プレイヤー1』に戻そう。ウェイド・ワッツ(タイ・シェリダン)が操作するアバター「パーシヴァル」は、創始者ジェームズ・ハリデーの過去の発言を閲覧し、「ときにはビルとテッドのように後ろへ戻れ」というメッセージに着目する。キアヌ・リーヴス主演の青春コメディ映画『ビルとテッドの大冒険』(1989)の物語は、頭が悪すぎて歴史の授業に落第しそうな高校生二人が、突然現れた電話ボックス型のタイムマシンを使って、歴史の授業を落第しないため本物の歴史を見学しにタイムスリップするという内容だった。
このヒントを参考に、パーシヴァルは第一の関門を史上初めて突破することに成功する。このヒントが真に語っているのは、「1980年代に戻れ」というメッセージである。それは、ジェームズ・ハリデーがOASISを作る原点となっている、ポップカルチャーと出会った子どもの頃の思い出がつまった時代だ。本作は2045年を舞台にしながら、1980年代を中心とした時代に、異様なまでに執着するのである。ゲーム、音楽、映画、アニメ…。様々にレトロな要素が、作品世界を埋め尽くしていく。
なぜ80年代なのか。アメリカの1980年代は、保守的な政治、大量消費文化が醸成されていくなかで、軽薄ともいえる表層的な「ポップ」表現が、創作物のなかで数多く見られた時代だ。その価値観のなかで、定番のアイコンとなる特徴的キャラクターやヒーローがたくさん生まれた。それは自分の現実の姿を好きな見た目に変えてそれらになりきれる、アバターの「表層性」とも連動している。
前述したように、格差が進行し現実の戦いから人々がドロップアウトし始めた現代社会をカリカチュアした時代が、本作の2045年であるのならば、そこに投影される、TVゲームやビデオの普及を中心に、大衆を楽しませるのための文化が花開いた1980年代という時代性は、現代をも含めた、それら全ての原点ということになる。意識の高い日本のラーメン屋が、ラーメンのルーツを求め中国へ旅に出かけるように、この「世界のはじまりへの旅」は、本質をつかむためには必然的な流れだといえよう。
90年代になると、そんな大衆の内面の問題がクローズアップされ、表層から自己の内側へとテーマが移行していくが、本作はやはりそこまでは踏み込まない。ここで大きなテーマとなるのは、そんな大衆的なポップカルチャーへの深い「愛情」である。
流行の移り変わりが早い大量消費社会を支えるのは、大企業の雇用主と、雇用されるクリエイターの、極度に効率化したシステムである。『機動戦士ガンダム』(1979)のなかで、兵器を開発する現場の技術士官が「偉い人にはそれがわからんのですよ」と、軍のトップの無理解を愚痴るように、両者には本質的に深い溝があるのが普通だ。作品を消費するユーザーは、その多くが企業から搾取される大衆そのものである。だから、開発費を投資して利益を目指す企業の役割よりも、自分たちの感性とつながりのある、実際の製品を生み出す能力のあるクリエイターを神聖視する。ジェームズ・ハリデーのように、技術者から企業家として、権力をつかみ取った人物は、大衆側から成り上がったヒーローとして崇め奉られるような存在になり得る。パーシヴァルが、80年代を象徴するジョン・ヒューズ監督の青春映画を例に、企業家のポップカルチャーへの理解を試し、仲間か敵かを判断しようとする背景には、そのような企業と大衆との関係があったのだ。