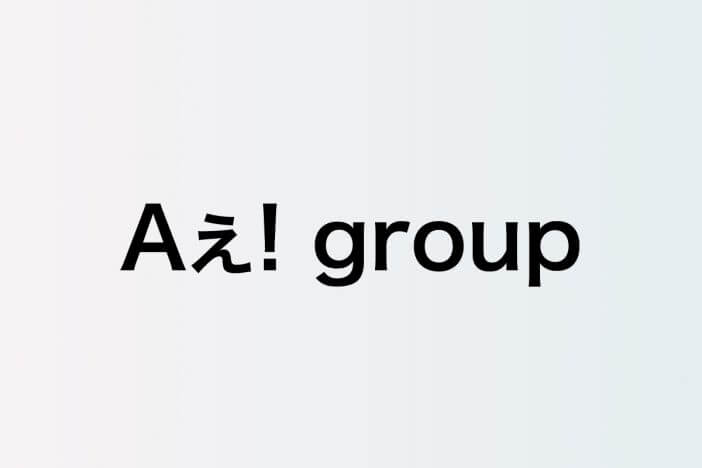Suchmos、新作『THE ANYMAL』サウンドの大きな変化 音楽シーンに一石を投じる作品に

Suchmosの新作『THE ANYMAL』はかなりの問題作だ。特にこれまで彼らの音楽を聴いてきた人にとっては、「変わった」というような言葉では物足りないくらいの大きな変化がある。
前作フルアルバム『THE KIDS』は大ヒットした「STAY TUNE」に代表されるようなUSのソウルやファンクの影響を消化して作られた音楽からの影響を感じた。メディアでジャミロクワイの名前がたびたび引き合いに出されていたが、スティーヴィー・ワンダーなどのニューソウルを引用しつつ、90年代のUKのクラブシーンの雰囲気を加えたジャミロクワイのサウンドはたしかにこの時期のSuchmosの影響源そのものと言った印象だった。とはいえ、ただの90年代の引用ではなく、リズムやハーモニーにはディアンジェロ的なネオソウルをアップデートした、ホセ・ジェイムズあたりの感覚が入っていたことで2010年代のサウンドになっていた。「STAY TUNE」をはじめとした楽曲には90年代だけでなく、80年代的なサウンドが感じられたのも、近年の80年代リバイバルを意識したものだろう。ディスコやAORやブラコン的なブラックミュージックの影響と近年のサウンドとの接点が聴こえていた。それは1stアルバムの『THE BAY』の延長線上にあるものだった。
というイメージで新作『THE ANYMAL』を聴いたら、あまりの変化にびっくりしてしまった。“転向”と言われても仕方がないくらいに、もはや別のバンドなのかと思うほどに音楽性が変わっている。
再生すると冒頭から前作とあまりに雰囲気が異なっていて戸惑うのだが、僕が感じたもっとも顕著な変化は、サウンドの質感がこれまでの彼らのイメージだった80年代や90年代のものではなく、60年代や70年代初頭のものだったことだ。冒頭の「WATER」からずいぶんレイドバックしていて、これまでのアーバンな感覚はなく、どこかドロッとザラッとしていて土臭い。そこから「ROLL CALL」を聴いてみると、さらにびっくりする。冒頭からひずみまくったベースラインに、サイケデリックなエフェクト、これもまたこれまでの彼らとは全く異なるイメージの60年代や70年代的なロックサウンドだった。
そこで少し前に出たEP『THE ASHTRAY』を聴いてみると、薄っすらその予兆はあることはわかった。ほとんどの曲はこれまでの彼らのサウンドの延長にあるものだったが、「VOLT-AGE」にはロック的なビートと暴力的な音色のベースラインとが走っていて、サイケデリックなエフェクトが施されていた。たしかにここですでに次作を匂わせている。ただ、そこで使われている音色はデジタルな質感のもの。音像はパキッとしていて、ロック的なサウンドではあるものの、これまで彼らがやってきた80年以降のブラックミュージックと通じるサウンドと並べても違和感のないものが選ばれていた。90年代的なオルタナティブロックや2000年以降のインディーロックと並べても違和感はないハイファイなサウンドだろう。音楽としてのベクトルはこれまでと違うが、響きや手触りは遠くないものになっていることもあり、「VOLT-AGE」はこのEPに自然に収まっていた。
それが『THE ANYMAL』になるとアナログな質感で、ザラッとしていて、スモーキーで、角が取れたサウンドになっている。例えば、それは現代のアーティストだと、ジャック・ホワイトだったり、The Black Keys(やメンバーのダン・オーバックのソロ)だったりと、ヴィンテージなサウンドを志向しつつ、その質感を新鮮に聴かせようとしているバンドや、なんならTedeschi Trucks Bandあたりのオールドスクールなアメリカのゴリゴリのブルースロックバンドあたりとも通じるものかもしれない。
特に「Indigo Blues」は現代のものというよりは、1964年から1970年ごろまでのサイケデリックなロックの雰囲気を再現しているサウンドで、1970年代以降のプログレッシブロックや、ハードロックの時代になる前までの非常に限られた時期に生まれたロックの感触をピンポイントで狙ってるように思える。サイケデリックな部分ではJefferson Airplaneや最初期のPink Floydあたりを思い起こさせるし、もちろんThe Beatlesも浮かんでくる。しかも、そのサイケデリックさもきらびやかでカラフルなものではなく、ダウナーでとろーんとした類のもの。Tame Impalaあたりのインディーロックのそれとは異なる。
そのサイケデリックなロックバンドたちがドラッグで覚醒しながらワンコードのブルースを演奏し、徐々に演奏時間が長くなり、サウンドが抽象化していったことを思わせるように、ここでのSuchmosも多くのポップソングにあるようなAABA的な構造ではなく、特に大きな展開をしないまま曲が進み、そのまま終わっていく。サビらしいサビと言える部分もあるようなないような曲で、少なくとも「歌いたくなる」類のわかりやすさやキャッチーさがある曲では決してない。前半部の6曲はあの時代のロック特有のかっこいい“だらしなさ”が前面に出ていて、かなりチャレンジングだ。
またところどころに顔をのぞかせるリズム&ブルースやソウルといったブラックミュージックの感覚もロック経由に聴こえるもので、The Bandや、The Animals、デラニー&ボニーあたりのスワンプロックを想像したりした。前作でジャミロクワイをイメージさせていたように、直接的にUSのブラックミュージックを感じさせるというよりは、そこに感化されたサウンドからの影響が聴こえる。ここでも1つフィルターを挟んでいるあたりに彼らのオリジナリティがあるのかもしれない。とはいえ、前作とは違い圧倒的に“渋い”センスが鳴っているのだ。