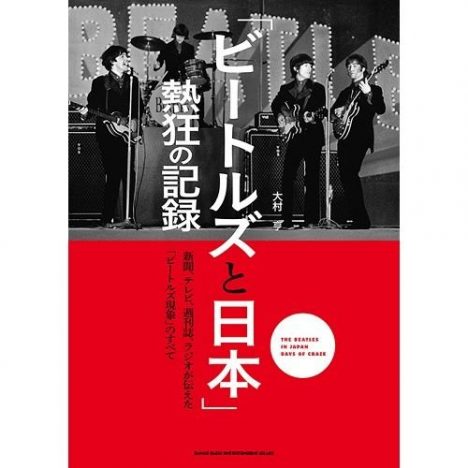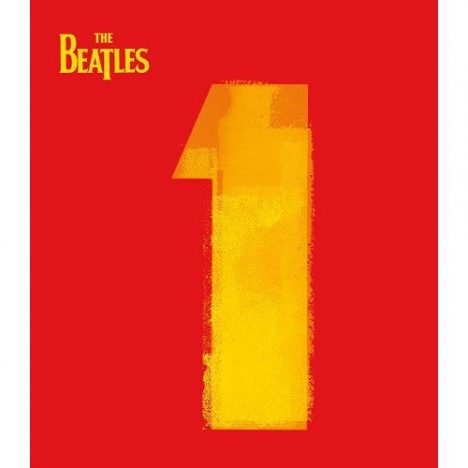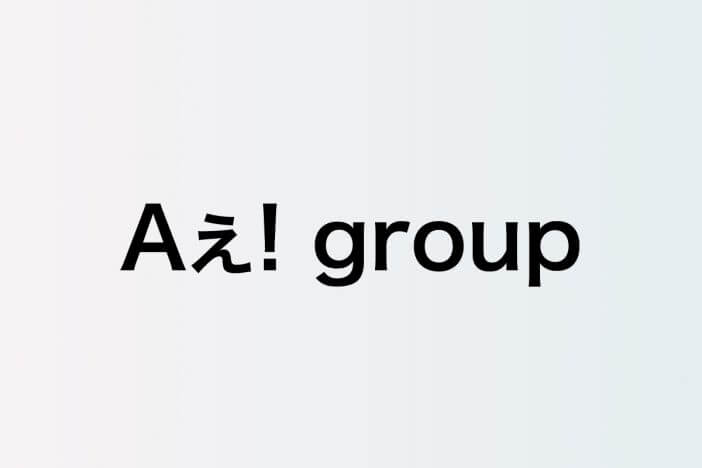“今”ビートルズに何を求めていたのか? 映画『イエスタデイ』&最新リミックス版で感じた喜び
なぜ私たちは、繰り返しリイシューされるビートルズのカタログに毎回一喜一憂してしまうのだろう。
そう、またこの季節がやってきた。彼らにとって、実質上のラストアルバム『アビイ・ロード』がリリースされてから今年で50年。それを記念し9月27日に、『アビイ・ロード』50周年記念エディションがリリースされたのである。
このアルバムは、『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』から続く「50周年記念エディション」のシリーズの一環で、ビートルズの「第5のメンバー」とも言われたプロデューサー、今は亡きジョージ・マーティンの息子であるジャイルズ・マーティンが中心となってサウンドプロダクションを務めている。
ジャイルズがビートルズのアーカイブシリーズに関わるようになったのは、シルク・ドゥ・ソレイユのサントラ盤として作られた2006年の『ラブ』から。この時は父ジョージとの共同プロデュース名義で、ビートルズの楽曲を素材から再構築していくという「荒技」を披露し物議を醸していた。あれから13年。ビートルズやその周辺作品のリミックス、リマスタリングなどを数多く手掛けてきた彼は、そのたびに目覚ましい成長を遂げ(2019年8月に公開された、エルトン・ジョンの伝記ミュージカル映画『ロケットマン』でもサウンド・プロデュースを担当)、今回の『アビイ・ロード』のおけるリミックスワークはその集大成ともいうべき内容となっている。
時期的に『アビイ・ロード』は、ビートルズの作品の中で最も「現代」に近いものとなる。であれば、リミックスを施したとはいえ先の『サージェント・ペパーズ~』や『ザ・ビートルズ』(通称“ホワイト・アルバム”)と比べると、音像的な違いはそれほど感じられないのではないかと、筆者は思っていた。が、蓋を開けてみれば『アビイ・ロード』2019年版は、これまでのどのアルバムよりも「攻めた」ミックスだった。
ジョン・レノン曰く、「好きな奴なんて一人もいない駄作」の「マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー」は、当時ジョージが持ち込んだモーグシンセサイザーの音色がこれまで以上に際立ち「変態ラウンジポップ」に生まれ変わり、ヘヴィなブルーズナンバー「アイ・ウォント・ユー」の後奏では、入り乱れるビリー・プレストンのハモンドオルガンと、ホワイトノイズがグッとフィーチャーされ、シューゲイザーも「かくや」と言わんばかりのサウンドスケープが聴き手の思考を停止させる。もう、かれこれ何百回、いや何千回と繰り返し聴いてきたはずの『アビイ・ロード』が今、全く新しい響きをたたえて目の前に蘇っているのだ。
そこで冒頭の疑問である。そもそも私たちは、なぜ最新リミックスが施されたビートルズのアルバム、いわば「過去の遺産」を、これほどまでにありがたがって聴いているのだろうか。「ジョンの声がオリジナル盤より生々しく聴こえること」とか、「ジョージ・マーティンによるオーケストラアレンジがより美しく胸を打つ」こと、「ポールのベースがよりファンキーに響くこと」が、なぜそんなにも嬉しいのか。
きっとそれは今言ったように、ビートルズの楽曲を「全く新しい響き」で聴いてみたい、もっとはっきり言えば、「生まれて初めてビートルズを耳にしたときの感動」を、再び手に入れたいからなのではないか。
私たちは、どうあがいても「初めての感動」を再び味わうことは出来ない。ましてやビートルズだ。物心ついたときには街中で、テレビで、映画館で流れていた彼らの「イエスタデイ」「レット・イット・ビー」「ヘイ・ジュード」を、生まれて初めて耳にしたときのことなど覚えていない人の方が多いだろう。そう、だからこそ私たちは、その「あらかじめ失われてしまった初体験」を取り戻したくて、ビートルズの最新リイシューが届けられるたびに、その細かな「差異」をめぐって一喜一憂しているのかもしれない。