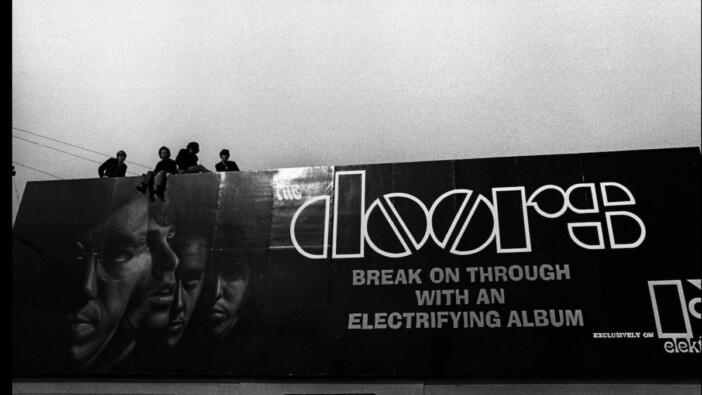チャゼル×ゴズリングが繋いだ“月とキッチン” 『ファースト・マン』深い悲しみと向き合う物語に

ジャズ・スタンダードとして知られる「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」がヒットしたのは1962年のこと。当時、ソ連と宇宙開発競争を繰り広げていたアメリカは、ソ連に先駆けて人間を月に送り込むアポロ計画を発表したばかりで、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」はアポロ計画の応援歌のような役割も担っていた。<私を月に連れて行って 星たちの間で遊んでみたいの>。そんなロマンティックな歌と裏腹に、宇宙飛行士たちは厳しい訓練に明け暮れていたのだ。そんななかで初めて月に降り立ったニール・アームストロングとは、どんな男だったのか。その素顔に迫るのが、『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督による最新作『ファースト・マン』だ。

物語はニール・アームストロング(ライアン・ゴズリング)が空軍のテスト・パイロットだった頃、1961年から始まる。アームストロングの幼い娘、カレン(ルーシー・ブロック・スタッフォード)が重い病気を患い、アームストロングと妻のジャネット(クレア・フォイ)は懸命に看病するが、二人の願いは叶わずカレンは亡くなってしまう。最愛の娘を失ったアームストロングは、その悲しみから逃れるように、NASAのジェミニ計画(アポロ計画の前段階のプロジェクト)に応募。宇宙飛行士候補生として厳しい訓練をこなしながら月を目指す。

本作の企画がチャゼルに持ち込まれた時、チャゼルは宇宙に興味を持っていたわけではなく、アポロ計画のことやアームストロングのことはほとんど知らなかったという。しかし、アームストロングの自伝を読んだことで、いかにアポロ計画が無謀な試みだったのかを知り、同時に英雄のイメージとはかけ離れた物静かな男、アームストロングに興味を持った。そこでチャゼルが大切にしたのがリアルさだ。彼は現代の乗用車にも及ばないテクノロジーで月を目指す人々の物語をドキュメンタリー・タッチで描き出し、狭いロケットのコックピットに押込められている宇宙飛行士たちの息苦しさも伝わってくる。そういった生々しい感覚を観客にも味わってもらうため、できるだけCGは使わずセットを作って撮影。宇宙のシーンでは、ロケットの窓の外にLEDでNASAの資料映像を映し出し、ライアンはその映像を実際に見ながら演技をした。そんな風にニールの視線やリアリティにこわることで、チャゼルは月への旅を疑似体験させてくれる。

そして、チャゼルは壮大なミッションに向き合うアームストロングの苦難の日々を描く一方で、家庭人としてのアームストロングにも焦点を当てる。初期の段階から本作に関わっているライアンは、チャゼルに「月とキッチンを繋ぐような作品にしよう」と提案したとか。「キッチン」とは家庭のこと。本作ではジャネットや子どもたちとの関係が、「月」パートと同じくらいしっかりと描かれている。アームストロングは口数が少なく、感情をあまり露わにしないので、「キッチン」パートで彼の素後や人間性を垣間みることができるのだ。ライアンは抑制された演技で、アームストロングのなかに潜む勇気や不安を表現。なかでも、娘を失った悲しみがアームストロングの人物像を組み立てるうえで重要な要素になっていて、アームストロングのどこか悲しげな眼差しが印象的だ。