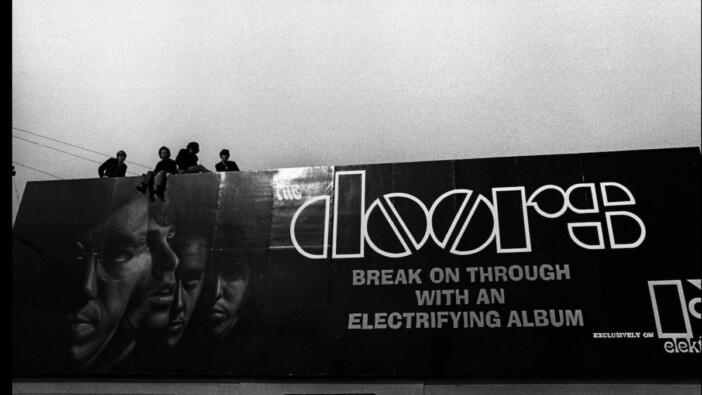人生なんて88分もあればじゅうぶんだーー『COLD WAR あの歌、2つの心』が描く愛と絶望

わずか88分の上映時間のうちに、悠遠たる人生の有為転変が、まるごと入っている。私たちは決して長くはない時間を劇場の暗闇で過ごし、あるカップルの愛と生と性、そのすべてを味わい、激しくぶつけられ、暗闇が暗闇でなくなった時、現実の時間感覚を取り戻すのに少し苦労するだろう。
タイトルは『COLD WAR あの歌、2つの心』。監督は、前作『イーダ』(2013)でアカデミー外国語作品賞を受賞し、日本公開時も非常に好評を博したポーランドの映画作家パヴェウ・パヴリコフスキ。すでに61歳となっているが、1990年代にはイギリスでテレビドキュメンタリーの仕事に従事していたそうだから、映画作家としては新鋭として考えてもいい存在だ。その『イーダ』の好評から次回作の発表まで5年も要してしまったのはいかにも惜しいことだが、その間パヴリコフスキは、激しい恋愛でクッツイタリ離レタリをくり返した両親の生涯を映画化しようと、もがき苦しんでいたのだという。結局彼は両親の実話映画化を破棄し、音楽家カップルのストーリーに置き換えた。それが『COLD WAR』だ。本作は昨年のカンヌ国際映画祭に正式出品され、監督賞を受賞している。

映画の最初、ポーランドの田舎を回って採集される民謡の数々が素晴らしい。このフィールドワークが母体となって、才能と容色の良い若者たちを選抜し、ポーランドの民俗芸能を総合的に教えこむ施設「マズレク」が誕生する。「マズレク」の女生徒で才能はあるが問題児のズーラ(ヨアンナ・クーリク)、そして「マズレク」の音楽監督兼ピアニストのヴィクトル(トマシュ・コット)。この2人の激しい恋愛が、時を変え、場所を変え、たがいの環境を変え、熱い調子で描かれていく。

一見して抱く印象は、とにかく精緻なフォーカスと完璧な照明によるモノクローム映像だ。今どき珍しくなった1:1.33のタテヨコ比によるスタンダード画面は、ノスタルジーよりもむしろSF的な神秘性さえ放っている。撮影は『イーダ』でアカデミー撮影賞にノミネートされたウカシュ・ジャル。おもしろいのは、ヴィクトルが東ベルリン経由でパリに亡命してからの画面が、それまでのスーパーリアルな神秘主義から、ややノスタルジックな画調に転調していく点だ。彼がパリに居を移した1950年代前半は、ジャズ全盛の時代で、本作で造成されたサンジェルマン=デプレあたりとおぼしきジャズクラブ「L’Éclipse(レクリプス)」は完全にボリス・ヴィアンが描くノワールなジャズ世界だ。ふと私たち観客は、心を揺さぶってやまぬ次の言葉を呟くことになるだろう。「ヌーヴェルヴァーグ」と。ヌーヴェルヴァーグ前夜のパリで、彼は夜な夜なピアノを弾き続ける。あともう少しでルイ・マルが『死刑台のエレベーター』(1957)を、フランソワ・トリュフォーが『大人は判ってくれない』(1959)を、ジャン=リュック・ゴダールが『勝手にしやがれ』(1959)を撮ることになるパリで。